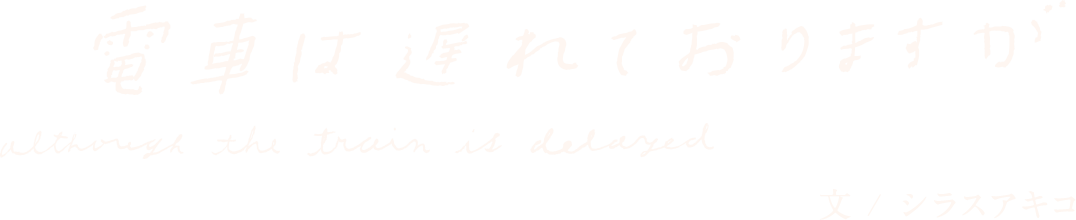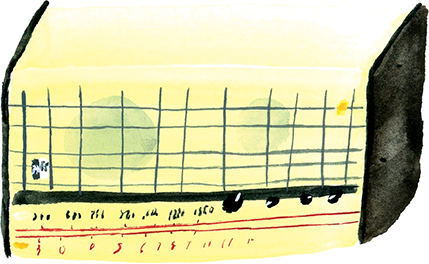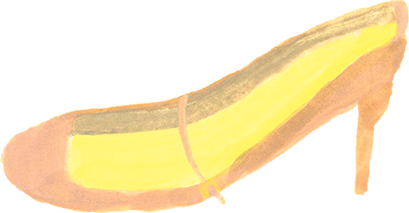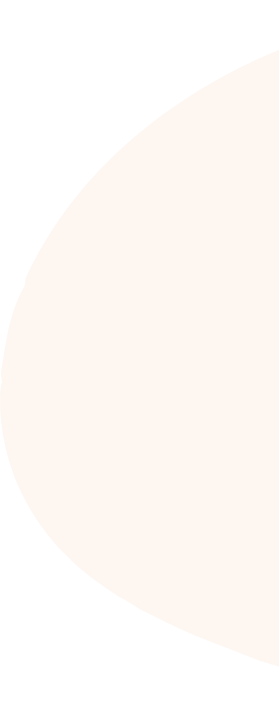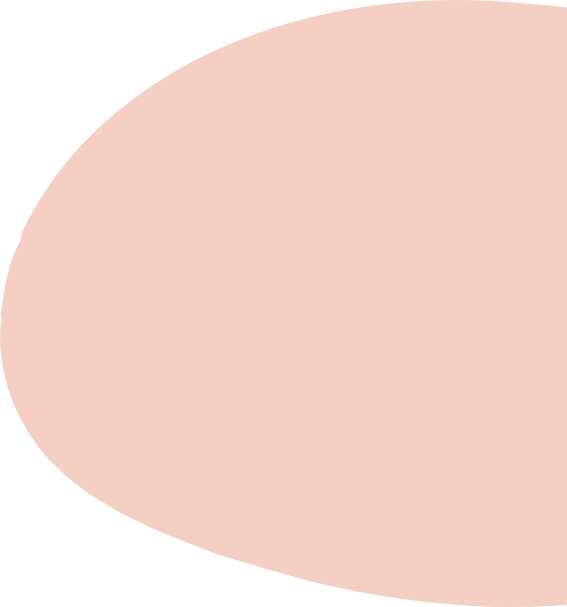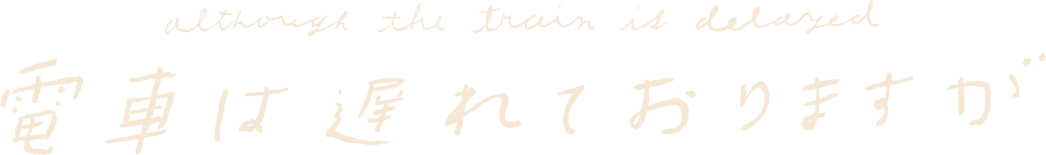僕が知らない彼女。
彼は母親からおつかいを頼まれるのが好きだ。自転車でこっそりと遠回りをして、あのこの家の前を通って帰れるから。
教室の窓ぎわに座って、ぼんやり外を眺めている彼女。ゆっくりと本のページをめくる彼女。友達のジョークに目を細めて笑っている彼女。そのすべてが謎めいていて魅力があった。自分とはかけ離れた、星の住人のような気がするのだった。
おつかいの帰り道、自転車のハンドルを握る彼の手は冷たく固まっている。でも彼女の家の屋根が見えてくると、胸の真ん中あたりがドクンドクンと熱く沸いてくる。彼は大きな木の陰に自転車を止めて、2階の窓を見上げてみる。しんと静まり返っている。この家で彼女は眠ったり、髪をとかしたり、ごはんを食べたりしているのだ。
「おばあちゃーん!私もー!」家の中から聞こえてきたのは彼女の声だった。学校で聞く声とは別人のように活発で、どこかユーモラスでさえあった。彼はペダルを強く踏み込み、逃げるように自転車を走らせる。誰も知らない、もうひとりの彼女を知った気がした。罪悪感と親近感と後悔がごちゃまぜになった。自転車のカゴに入った牛乳が大きく波打っている。
*「電車は遅れておりますが」は毎週火曜日に更新しています。