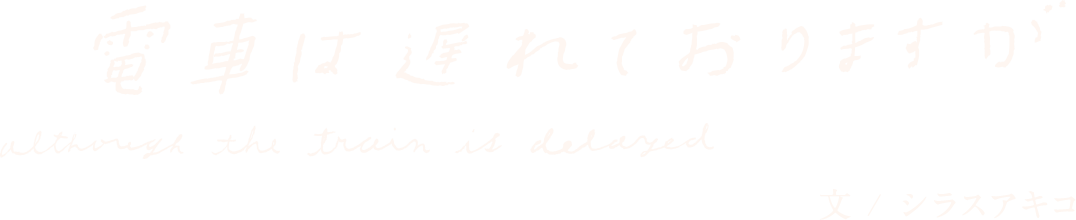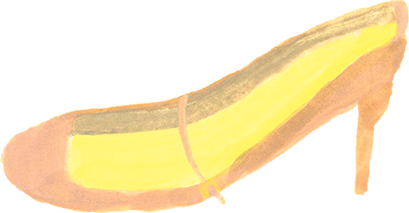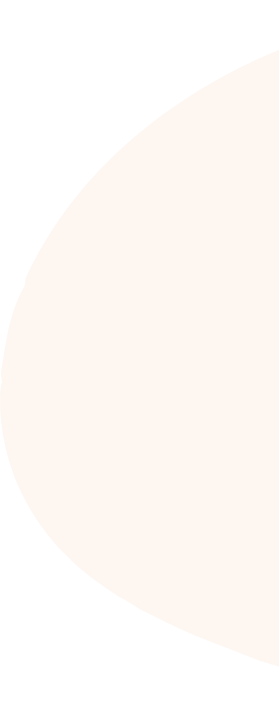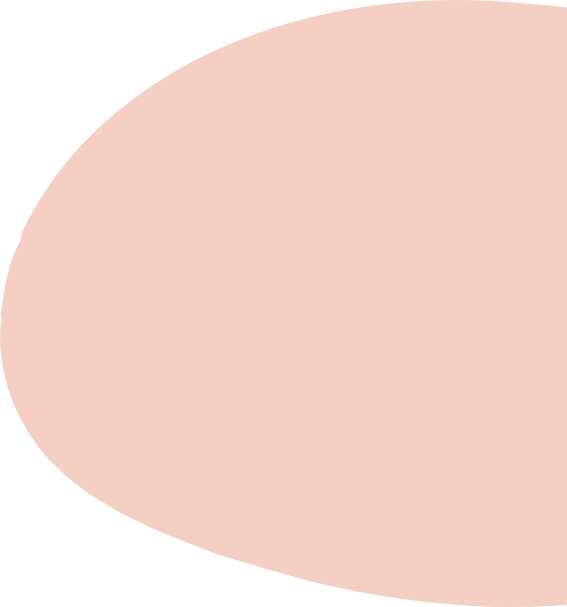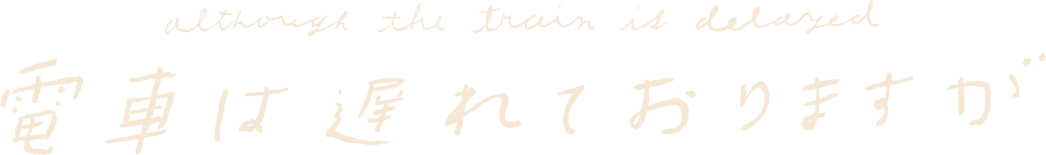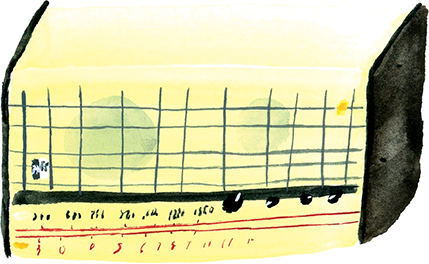
サーヴィスを変えてみましたの。
わたくしが瓶ビールの栓を抜く“コスン”というオトを、
好まれるお客さまが多いのです。
だからBARから音楽を無くしました。
わたくしが濃紺か黒のドレスしか身につけないのは、
なんというかまぁ、照れもあるのでしょう。
淡い色などはどうも、ねぇ、性格は男なので。
わたくしは料理をしません。
缶詰を皿に盛ったり、サラミ、チーズなどをおだしします。
料理をしている姿は似合わないといわれます。
わたくしはあまり喋りません。
質問されれば答えますけれど、ひとこと、ふたこと。
静かに飲みたいお客さまの方が多いです。
あれこれとサーヴィスを考えることがすきです。
今度はこうしてみようかしらってね。
まぁ、いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。
*「電車は遅れておりますが」は毎週火曜日に更新しています。