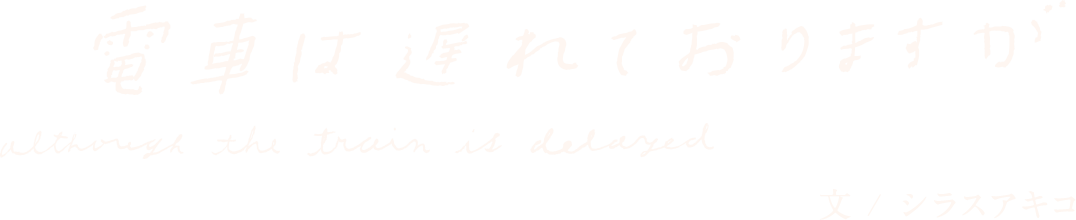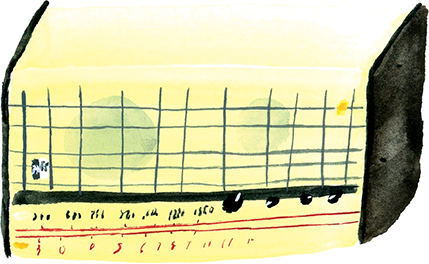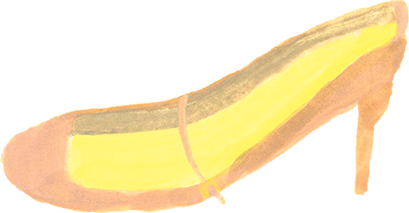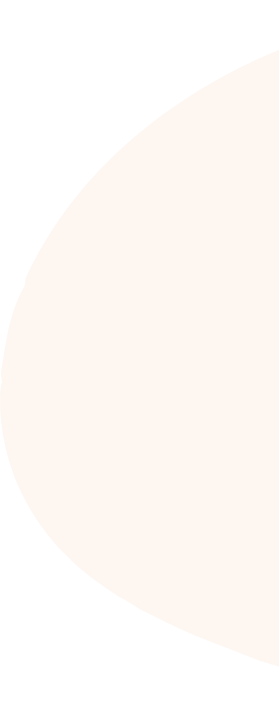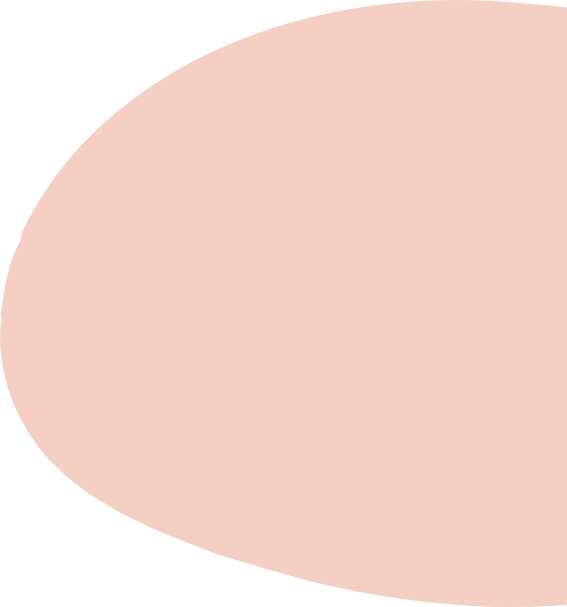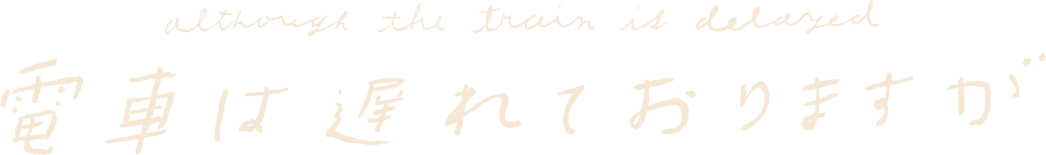自転車までの距離は遠かった。
日が落ちるのを待つと、彼は今日もひとり自転車に乗る練習を始めるのだった。(このことは親友にも内緒にしている)サドルにまたがり、つま先で地面を蹴って前へ進む。ペダルに足を置こうとしても、なかなかタイミングが上手くいかない。地球から身体がふっと浮いてしまう怖さといったらなかった。
ようやく右足でペダルを踏み込む。「よし!」と思った瞬間に、ハンドルは左右にグラグラと揺れ、派手に自転車ごと倒れてしまう。その場に座り込んで膝小僧をさする。血は出ていなかった。公園の木々は黒々としたシルエットに変わっていた。まぁまぁな絶望感が彼の中で広がっていく。