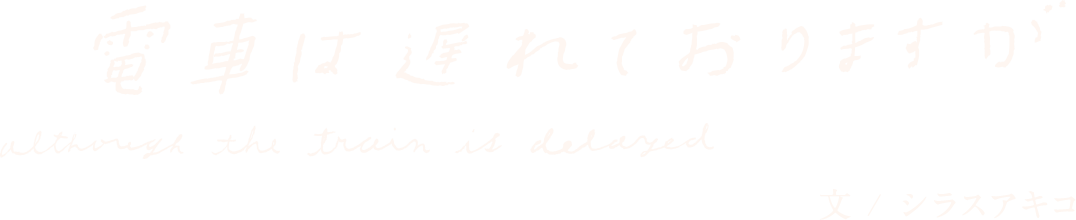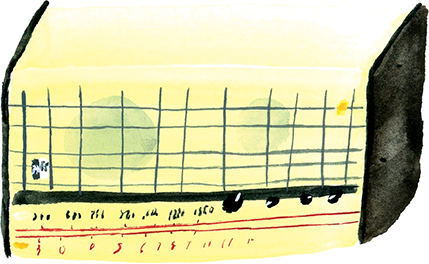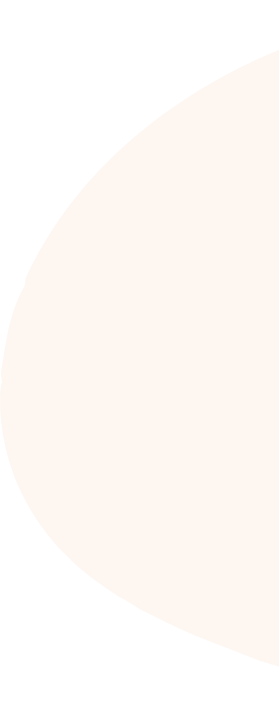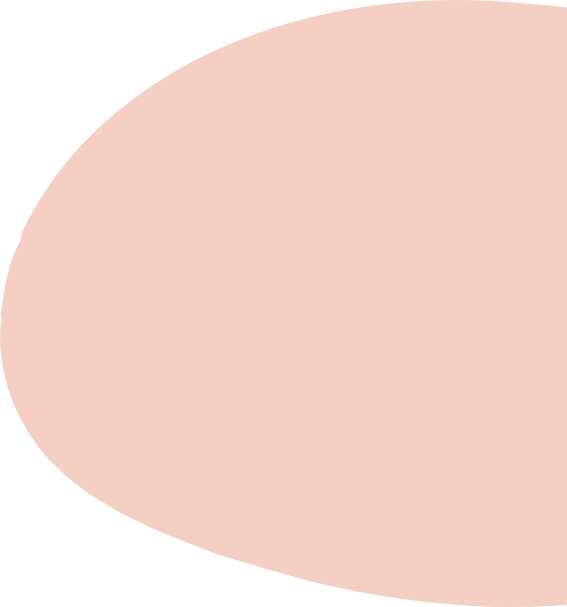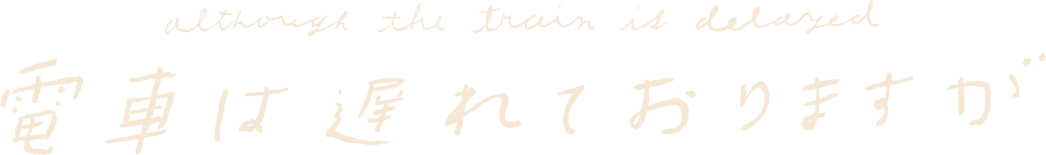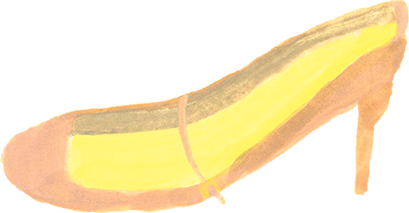
わたしはアシスタント。
エレヴェーターよりも階段の方が早いわ、と目で合図をおくったボスは、待ち人の列からはずれ薄暗い階段を登りだした。彼女も後に続く。安全ピンくらい細いヒールはボスのくるぶしを支え、階段を上がるたびにアキレス腱がくっきりと浮かびあがる。この後のミーティングが大荒れになることは、容易に想像できた。女性ふたりのヒールの音が揃って響きだしたから、彼女はわざとタイミングをずらした。今はアシスタントだけれど、このボスよりももっとしなやかに、もっとチャーミングに輝く日がくることを彼女は知っている。遠くでサイレンが鳴っている。