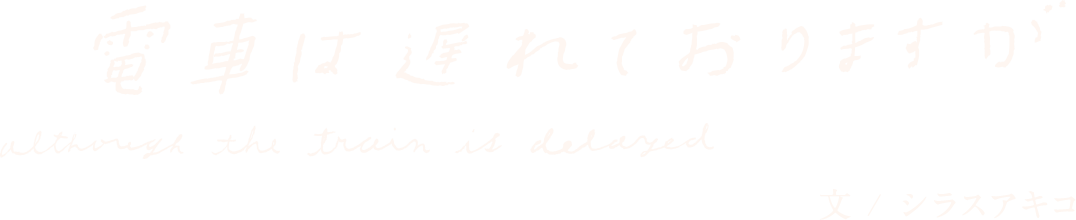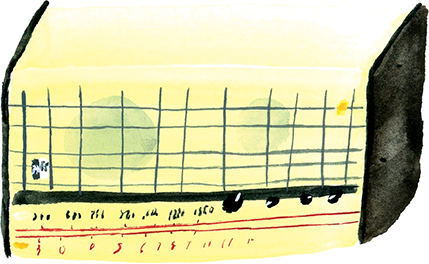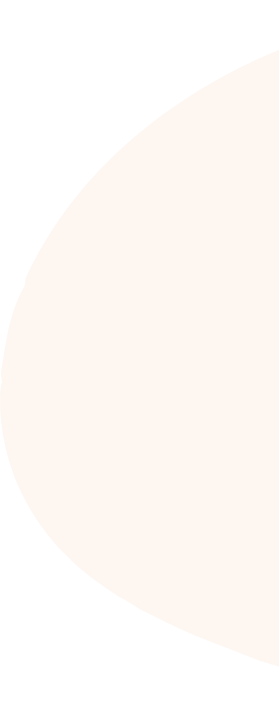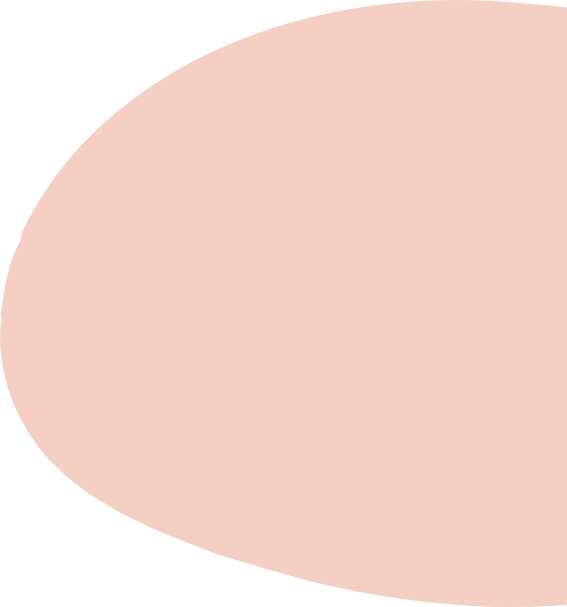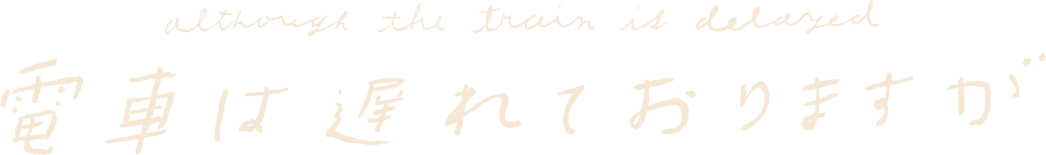114秒のホラー。
彼は石の階段をのぼっている。56、57、58…。こころの中で数えながら階段をのぼっている。69段をのぼりきったら我が家が見えてくる。もう少しだ。家を買ったのが4年前。そろそろこの階段にも慣れて良いはずなのに、息が上がるのが早まっているのは年齢のせいだろうか。夜が夏の夕日に溶け込みはじめる。この階段をのぼる者は彼ひとりだ。額の汗をぬぐうこともせず、彼はただ階段をのぼることだけに集中する。66、67、68…。
あと一段、というところで彼の目の前は真っ暗になった。とろりと身体が浮いた。次の瞬間、彼は階段の一番下でうずくまっていた。気を失っていたのだろうか。貧血をおこしたのかもしれない。でも、変だ。さっき68段までのぼっていたはずなのに。それとも階段をのぼる前に倒れてしまい、短い夢でも見ていたのか。彼はスーツについた泥をはたきながら立ちあがる。とにかく早く家に帰りたい。妻と子供たちの顔を見れば、今の不可解な出来事なんて忘れられるに違いない。さぁまた一段目からはじめるか。1、2、3、4、5、6…。今年最後の蝉が、ワンワンと競い合うように鳴いている。自分の吐く息が、蝉のテンポとシンクロしていく。そしてようやくここまできた。彼ははっきりと数字を声に出す。66、67、68…。
すると目の前が真っ暗になり、そして身体がその場からスライドする。気がつくとふたたび階段の一番下に倒れている自分がいた。「なんなんだ、一体」彼は両手を髪の毛の中に入れ、10本の指で自分の頭を鷲掴みにした。頭皮は汗でじっとりと湿っていた。彼は地べたにあぐらをかく格好で目を閉じ、深い呼吸をした。きっと疲れているんだ。帰ったらまず風呂に入ろう。そして夜はぐっすりと眠るんだ。彼は恐怖心を追い払うために、ごくごく日常の営みを想像してみた。つけっ放しのテレビ、子供たちがキャッキャと騒ぐ声、妻が食器を洗う音。いくらか気分が落ち着いてきた。ゆっくりと目をあけて、高く伸びる階段を仰ぎ見る。彼の目に飛び込んできたのは、ぞろぞろと階段をのぼっていく人たちの光景だった。ダッダッ、ダッダッ…!ダッダッ、ダッダッ…! 足音が規則正しく響きわたる。20人、いや30人ものスーツ姿の男性たちが、ただひたすら階段をのぼっているのだ。数秒後、彼は男性たちの後ろ姿がまったく同じであることに気がつく。そしてそれらが自分自身の後ろ姿であることも。
*「電車は遅れておりますが」は毎週火曜日に更新しています。