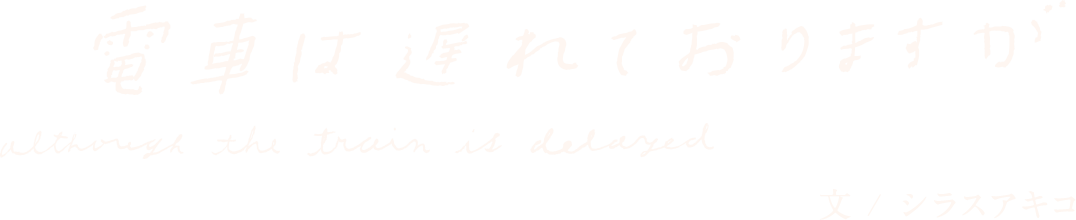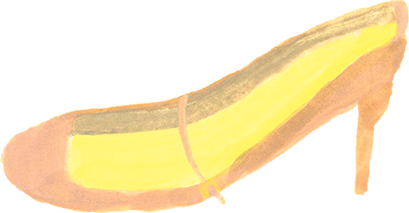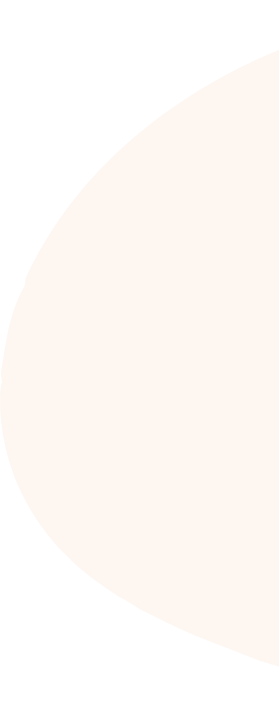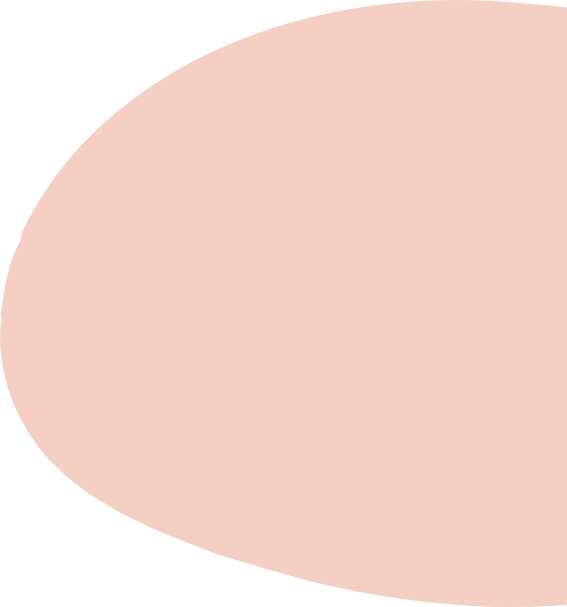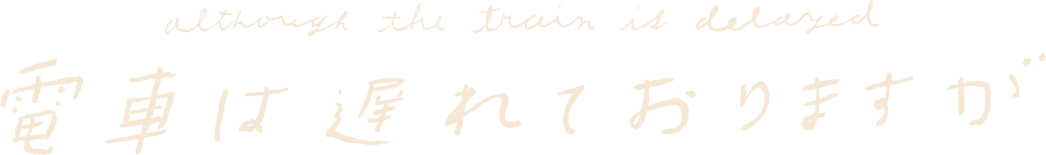考え事のゆくえ。
布団の中に入ってから、ずいぶんと時間がたっていることは彼女にもわかっていた。眠りに落ちる瞬間を“あ、いまだ”と見届けたい。そんな意識がじゃまをする。この国でこんな深夜まで起きている小学生は、きっとじぶんだけだ。胸の真ん中あたりに、シュワシュワと焦りのソーダ水が湧き上がる。真っ暗な部屋。真っ暗な口の中。音楽の授業で演奏した行進曲が、高らかに耳の奥から聞こえてくる。じぶんの心臓が同じリズムで打っている。朝をつかまえに、裸足のまま外へ出てみたらどうなるだろう。真っ暗な地面にストンと穴があいた。これが夢なのか想像なのか、考えることを手放そうとおもった。