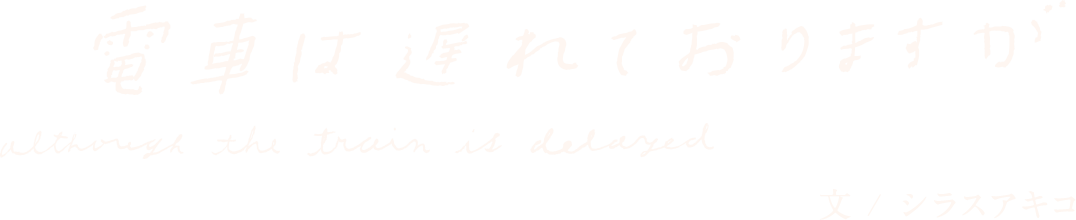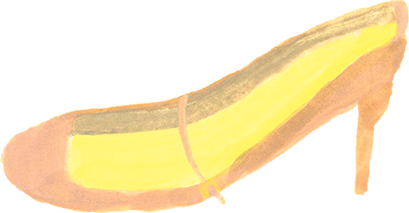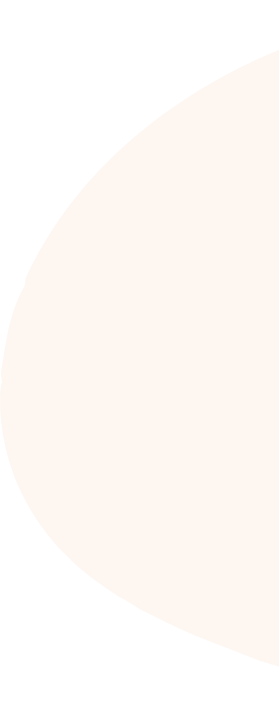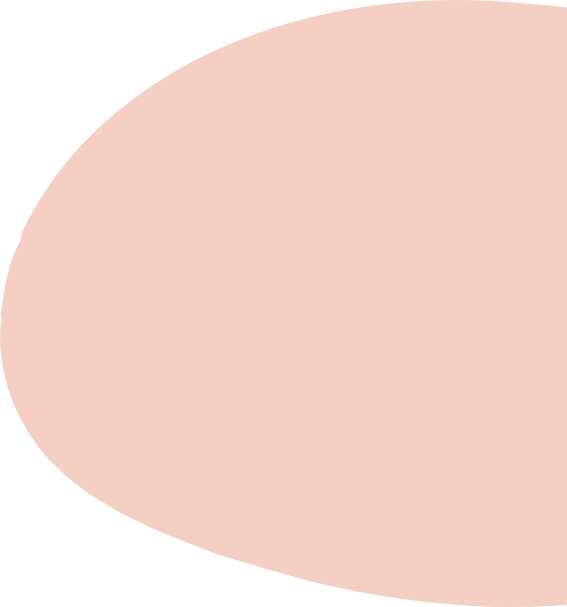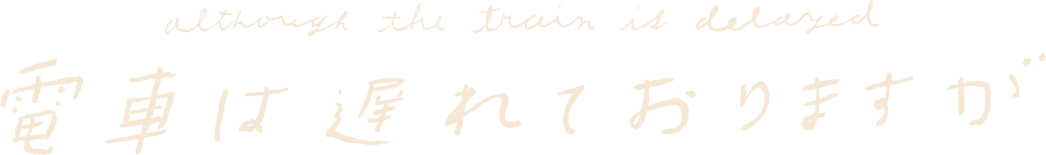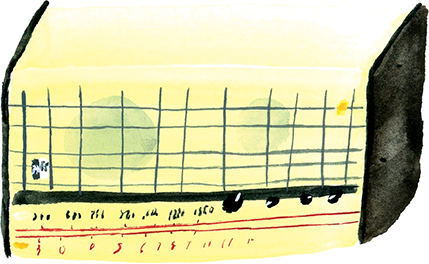
キッチンプロポーズ。
ビールグラスを冷やすのは彼の担当。おつまみを可愛く盛るのは彼女の担当。メインの肉を焼くのは彼の担当。最初に酔っ払うのは彼女の担当。3杯目から(やっと)饒舌になるのは彼の担当。どこか旅行に行きたいと言い出すのは彼女の担当。サラダの残りを食べるのは彼の担当。パリに行きたい!と叫ぶのは彼女の担当。どうせだったら新婚旅行にする?とつぶやくのは彼の担当。それって結婚するってこと?と聞くのは彼女の担当。うん!と頷くのは彼の担当。いいね!とニンマリするのは彼女の担当。何杯目かわからないビールをグラスに注ぐのは彼の担当。乾杯するのはふたりの担当。うとうと眠くなるのは彼女の担当。食器の後片付けは彼の担当。ソファーで夢を見るのは彼女の担当。