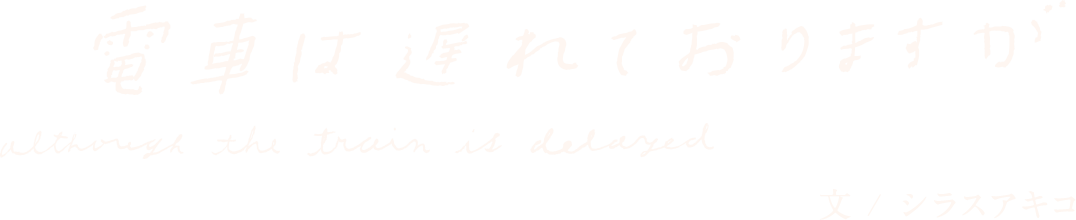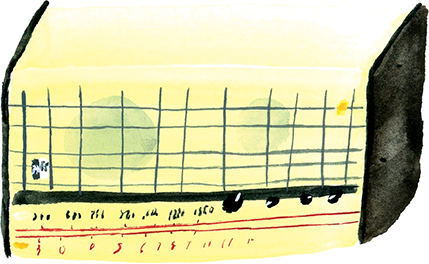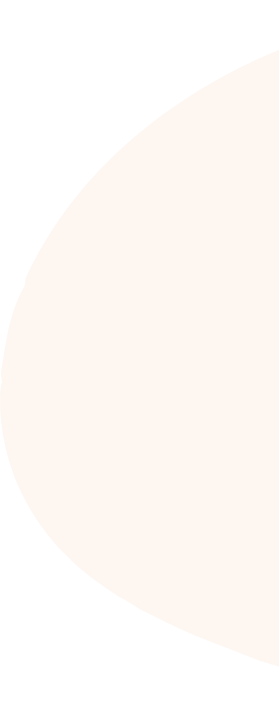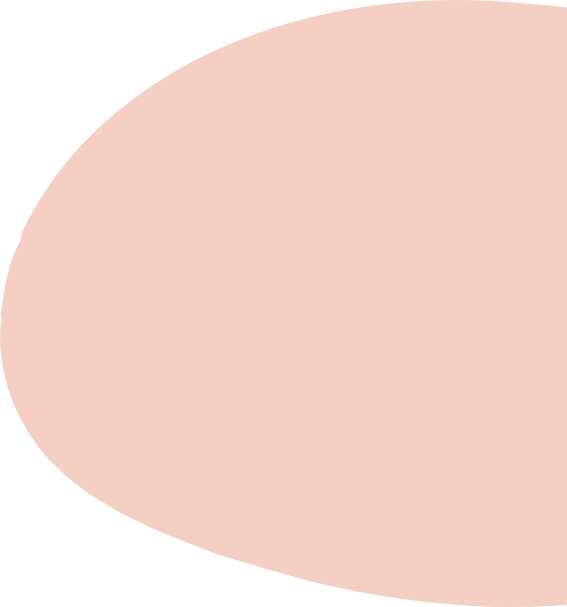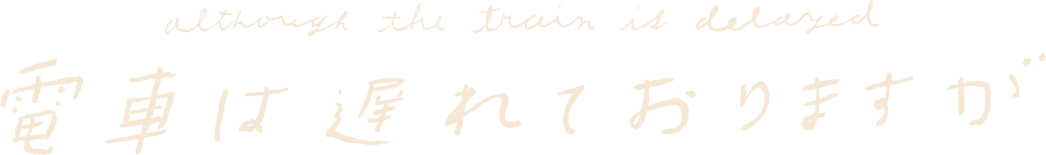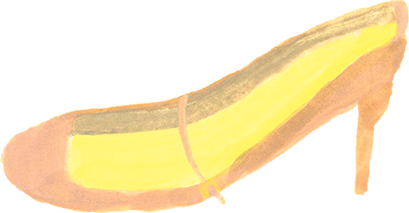
デリを買ってかえろう。
今夜は何食べる。何作る。それともどこかで食べて帰る。ううん、なんだか今日はイエ気分。賛成。生ハムなんて買ってみる。たしか冷蔵庫に白ワインあったはず。うわぁ急にお腹すいてきた。サーモンとブロッコリーのマリネもいいね。コロンとしたクリームコロッケもおいしそう。ローストビーフをちょこっと買おうか。黄色いカラシをつけて食べようよ。ついでにお花も買って帰ろうか。いいね。可愛いピンクのお花がいいな。(彼女は本日3人の男性から夕食を誘われたがすべて丁重に断った。なぜなら彼女はひとりで夕食を楽しむ才能があったから。)
*「電車は遅れておりますが」は毎週火曜日に更新しています。