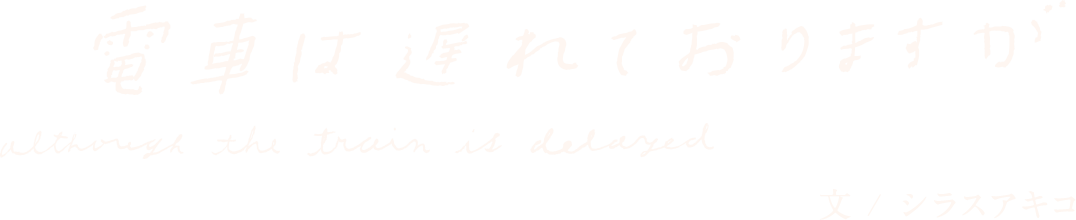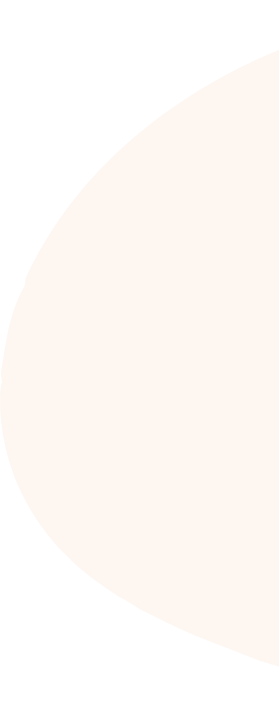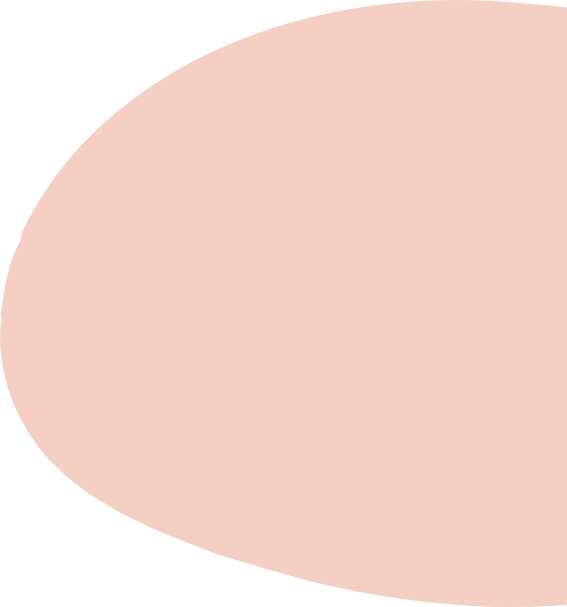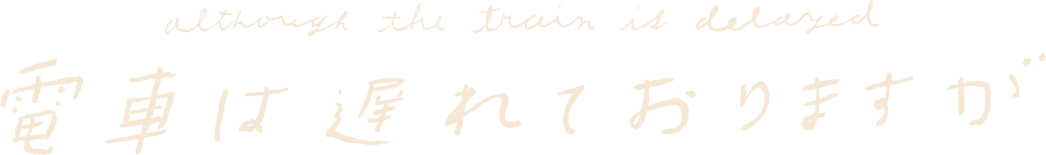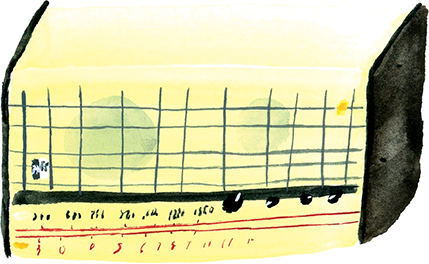
地球の見張り役。
ベッドから脚をおろすと、板張りの温度はほぼ足裏と同じくらいだった。朝まで眠り溶ける睡眠力を持った彼が、途中で目を覚ますのは珍しい。すべては夏の夜の仕業だった。家の中は真っ暗だし、まぶたも半分しかあいていないことから、用心深く歩こうとする自分自身に感心する。
キッチンに入ると、ブーンと鈍くて低い電子音がその場を仕切っていた。冷蔵庫のドアをあけると、青白い灯りと冷気があふれ出てくる。彼はその心地よさに一瞬目を閉じる。家の中で一番冷えた小さな部屋に、ずるずると入り込んで眠れたらどんなに幸せだろう。
冷凍庫にはキューブ型の氷がたっぷり出来ていた。彼は指で氷をつかむと、透明のグラスにわざと少し高い位置からカランカランと音をたてて入れた。次に水道水を細く注ぐ。氷と氷がくっつき、ミシッと鳴き声を発する化学反応を楽しむ。作りたての氷水を、一気に身体の中に流し込む。渋滞している道路を、スピードを上げて駆け抜けるイメージが湧いた。夏の夜の自分を、じっと見張っていてくれた冷蔵庫をふと振り返る。